100%土に還る「天草ヒノキのコンポスト」
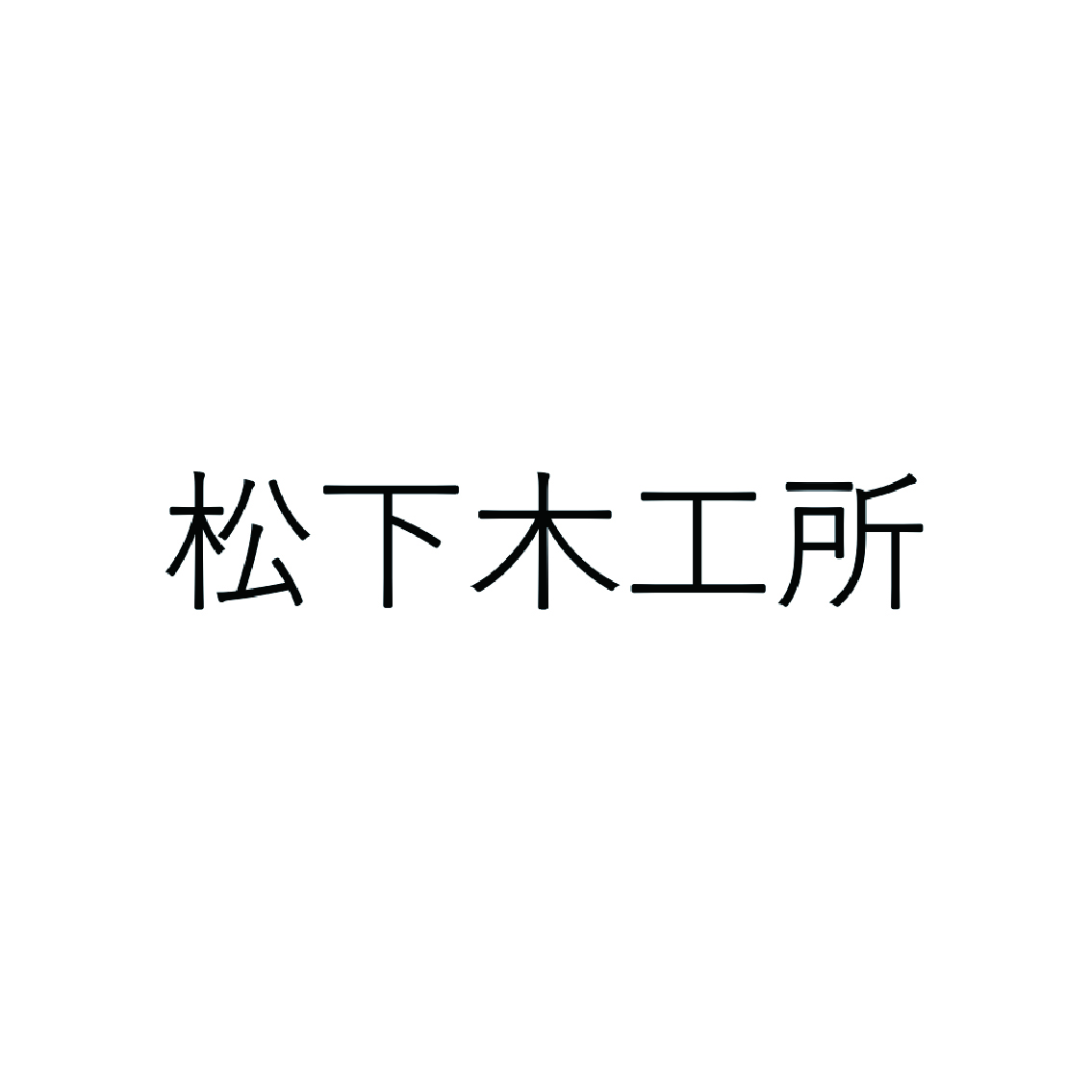 松下木工所
松下木工所「コンポストまでも土に還る」
「生ごみが減ってうれしい」「生ごみが堆肥になっていくのを見るのが楽しい」と昨今、コンポストを置く家庭も増えてきている。生ゴミが堆肥になってくれ、尚かつ悩ましい生ゴミも解消してくれる。とくに水を含んだゴミの処理にはエネルギーを必要とし、地球への負担もかかる。
そんなコンポスト自体までも地球に優しいものに作り上げたのが、松下木工所・Propeller(プロペラ)の松下さん。
『100%土に還る「天草ヒノキのコンポスト」』という名前通り、釘、接着剤を使わずすべて木で作り上げるコンポスト。自然に還る木を材料にすることで、製造から最終廃棄までの環境負荷を低減できる。
そんなコンポストの想いを探っていくと、もっと大きな地球の資源に対しての大きな想いがあった。
100%土に還るコンポストを作った松下さんの想いをストーリーを聞いた。

「天草の自然に囲まれて」
熊本県の青い海に囲まれた、大小120余の島々からなる天草諸島。そんな自然豊かな天草で生まれ育った松下さん。小さい時から海や山々で遊び、自然と共に生きることが自然と身についていた。

松下さんのお父さんは障子や襖などを作る建具屋さん。
小さい時から、物を作ることに囲まれて育ったので、松下さんも趣味で模型やプラモデルなど物を作ることが好きだった。
物を作ることは好きではあったが、自分の新たな道を見てみたいと、仕事を引き継ぐことはしなかった。
これからはコンピューターの時代だろうと高校卒業後は福岡のエンジニアの専門学校に進み、その後はエンジニアとしてプログラムを作り始める。
しかし、松下さんには同じ「作る」でも物体のないものを作るのと、肌触りのある物を作るのは気持ちの入り方が違う。やはり自分の指先を使って細かい作業をすることが合っている。エンジニアの仕事も2年半続けたが、自分に相応しい仕事を探すために退職を決意する。
やはり手の感触を感じながら作ることが自分に合うだろうと、天草に戻り、意を決して父親の建具屋を継ぐ決心をする。
「お客様の顔が見たくて」
数年ぶりに戻ってきた地元の天草。父親から建具屋としてのいろはを教わる。
7年の修行でようやく一人前と言われる建具の世界。昔気質の父親で、見て身体で覚えることが多かったが、元々製作をすることに親しんでいたおかげで、メキメキと建具職人としての技術を磨いていった。
建具職人としての仕事は父親の代から、工務店からの下請の仕事を請け負っていた。そのためお客さんの顔を直接見れずにいた。
そこで松下さんはしっかりと職人として購入者の気持ちや生活に合わせたものを作りたいと「Propeller」という名前で受注の家具製作も始めた。
使う人の一人ひとりの要望を組み込み、お客様の「想い」を家具に込める。 使う側と作る側が一緒に話し合いながら作る、世界にひとつだけのオーダーメイド家具を提案している。

こだわりは「使いながら育つ家具」ということだ。
松下さんはテーブルからキッチンなどをすべて木の素材で作っている。木の素材というと、腐ってしまうようなイメージがあるかもしれないが、よほど水浸しにしない限り腐る心配はない。
木の素材の良いところは経年変化があるところだ。良く使用する部分には、味が出てくるし、思い出が深くなっていく。
これがプラスチックの素材だと、作りたてが100点で、そこから少しでも傷がつくたびに、点数がマイナスにされていくものになってしまう。

木の素材は、もし家具に飽きがきたとしても、木材だけを他の家具に再利用することもできる。再利用するためにも木にウレタン系の塗料を使わないのが、松下さんの信条だ。なので自然塗料系の物を活用し、家具を製作している。
「天草ヒノキプロジェクト」
松下木工所・Propellerで木材加工をしているときは、海外の木材を中心に製作していた。
やはり海外の木材は、豊かな色合いや独特の木目が特徴で、家具や床材などのインテリアデザインにおいて非常に魅力的な要素ではある。
松下さんも海外の木材を使用して、家具を作ることが多かった。
しかし、松下さんの木材への価値観を変えてしまう出会いがあった。

それが「天草ヒノキプロジェクト」
天草ヒノキプロジェクトは、熊本県天草地域で行われている、地域のヒノキ材の活用を考え推進するプロジェクトだ。
海が注目される天草地域だが、実は豊富な森林資源を持ち、戦後に植林した山の木が、現在、使いどきを迎えている。そこで、森林組合や製材所、工務店や木工所など、これまで分断されていた業種が連携して、地域材を見つめ直した。

そもそも、なぜヒノキなのか?
天草の土地はヒノキの生育に適していた。
かつて天草地域に生育していた松がマツクイムシにより枯損し、その後、痩せ地の天草でも生育が見込めるという理由でヒノキが積極的に植林された歴史がある。そのため天草地域の人工林の約7割がヒノキで、杉が多い他の地域と比べると特徴的であるといえる。
そこで天草の中でヒノキの良さを知ってもらう「天草ヒノキプロジェクト」が始動した。
今までは海外の木材が好きだった松下さんも、この天草ヒノキプロジェクトに出会ってから、考え方が変わったと言う。
地元の天草にヒノキと言う資源があるのにもかかわらず、なぜわざわざ海外から高い木材を輸入して使っているのだろう?海外のものを使うためには、輸送のコストも燃料もその分かかってしまう。
目の前にある資源をさらに活用すれば地球に優しくなる。
「天草ヒノキプロジェクト」との出会いをきっかけに、地元の資源を使った家具づくりにも取り組みはじめたのだ。
「100%土に還るコンポスト」
天草ヒノキプロジェクトのメンバーで「資源を循環させるためのコンポストだから、コンポスト容器も循環する素材であってほしい。木で作れないか?」という話になった。
生ゴミの堆肥化、資源化という行いに加え、その容器にまでこだわりたい方へ向けてのコンセプトでコンポストを作りたいと松下さんに相談された。
打診された松下さんも、最初はOKを出すことができなかった。
コンポストは物自体も大きいし、堆肥などを詰め、それなりに強度も必要。それをどうやって釘無しで作れるのであろうか。
「真に資源を循環させるコンポスト」の設計図を考えあぐねていた。

そんなある日、アイディアが突然降り注ぐ。
夢の中にログハウスが現れたのだ。コンポストも木を長い1枚の板にして、ログハウスのような形に組めば大丈夫だという発想に至った。
実際にヒノキをログハウスのように組み立てる形にしたら、強度も充分ある。
組み立てるのも、重ねるだけの簡単な作りなので誰でも5分ほどで完成できる。
地元の恵まれたヒノキという資源を活用した、釘や接着剤を一切使用しない100%土に還るコンポストが完成した。

このコンポストはヒノキで作ったからこそのメリットも多くある。
まず木でできているので、大きさは自由にオーダーができる。高さなどは要望があれば、大きく作り変えることも対応できる。これがプラスチックならば、大きさを作り変えないといけない。
このコンポストを購入してくださった方々からの感想によれば、箱を開けた瞬間からヒノキの香りが漂ってくるとのこと。まるで森林の中にいるような感覚を与えてくれる。

ヒノキの香りにはリラックス効果もある。その心地よい香りが漂ってくるだけで、ストレスが和らぎ、心が癒される感覚に浸ることができる。
コンポストの使用は、廃棄物の処理だけでなく、心の癒しやリフレッシュの一環ともなるのだ。
家族でヒノキの感触を感じながら、木の温もりを感じるのも良いだろう。

もちろんコンポストを最後まで使用していただけることが一番の喜びではあるが、コンポストとして使わなくなったとしても、ヒノキを別のものに活用もできる。最終的には燃やして自然に返すこともできるので、正真正銘の100%土に還るコンポストなのだ。
「引き算で地球を考えていく」
これからの地球に思うことを聞いたら「引き算をして人間の生活を考えていきたい」と松下さんは語っていた。
私たちは日常生活の中で、常に新しいものや満足感を求める傾向にある。しかし、時には新しいものを追い求める前に、現在の生活において不必要なものを見つけることが重要かもしれない。もしかしたら、私たちが本当に必要としているものは、すでに手元にある。
例えば、過剰な物の所有や無駄な消費は、環境への負荷を増やす原因となる。地球上の資源は限られており、持続可能な社会を築くためには、必要最低限のものにフォーカスし、節約やリサイクルを心がけることが求められるだろう。

また、物に執着することは、心の自由さや創造性を制限してしまう。不必要な物に固執せず、心を解放して新しい体験や思考の幅を広げることが、より人間らしい生活を築く鍵となるかもしれない。
持続可能な生活を築くためにも、必要なものと不必要なものを見極めることが求められるのだ。
このコンポストも地元、天草にあったヒノキという資源に新たに目を向けて製作したものだ。
「目の前にある資源を活用しよう」そんな想いがコンポストから届くと嬉しい。
