珈琲道の庵治石ミル(鏡肌)
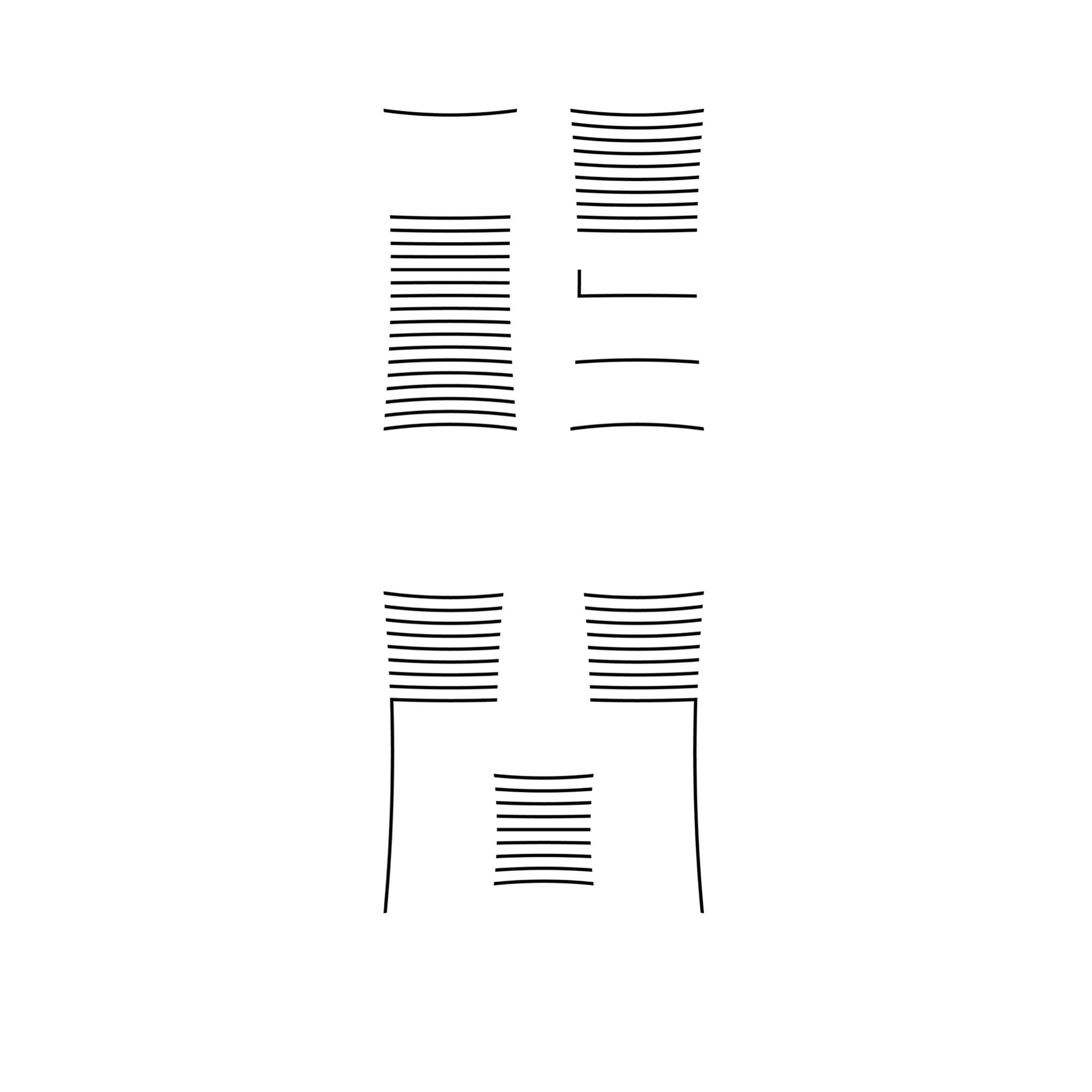
Transparency Points
透明性項目
品物のハイライト
この品物の注目して欲しいポイント
作り手
品物の生産に関わった作り手の顔とコメント
生産地
品物が作られた場所
原材料
品物の素材や原料
庵治石
100%
SDGsへの貢献
この品物がどのSGDsに貢献しているか
庵治石は、花崗岩の中でも高い硬さを兼ね備え、風化にも強く、長期間利用し続けることができます。
レア度
品物の希少性
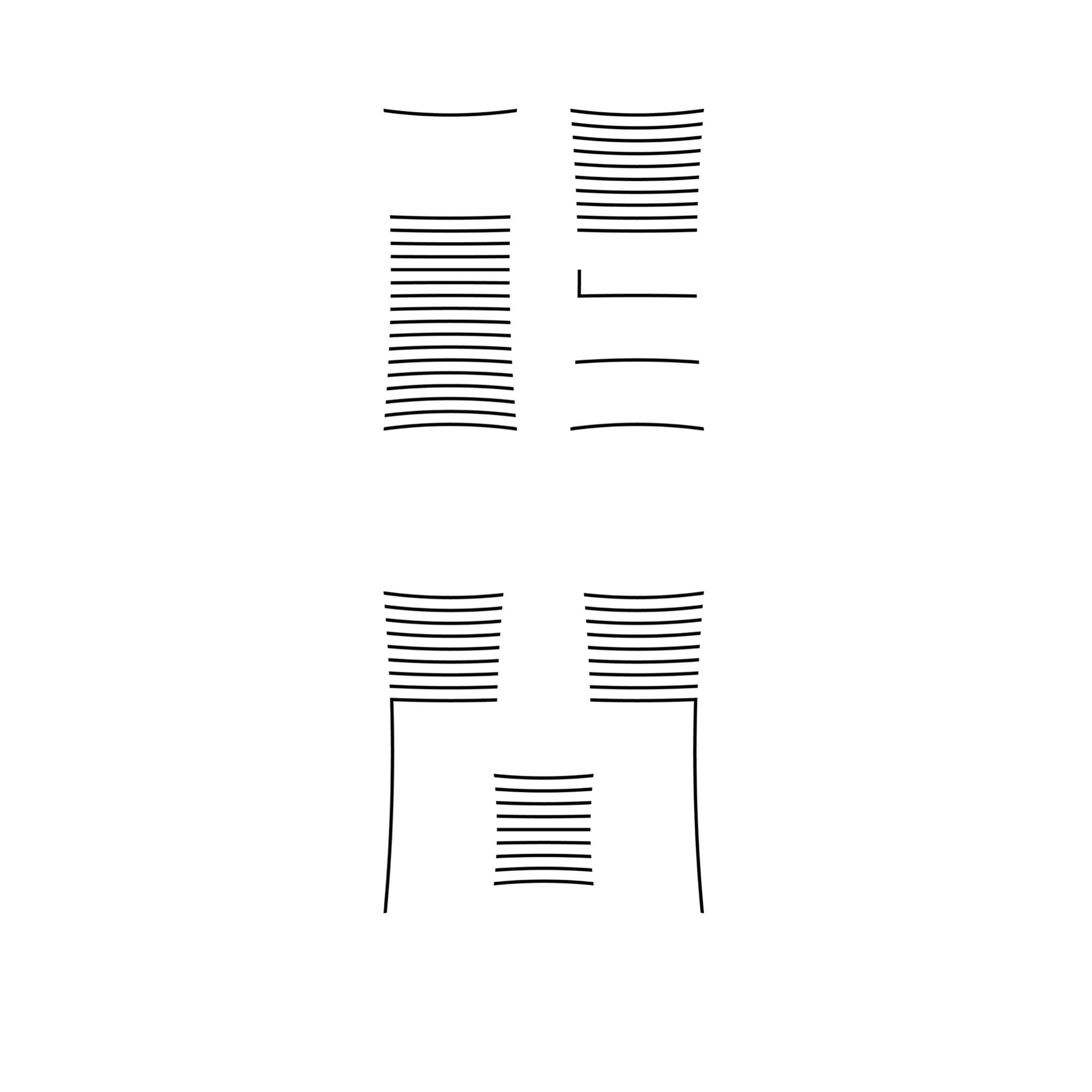
Story
品物のストーリー
現代社会で鈍化している身体感覚を呼び覚ます、石ミル
醒間が提供する体験。それは、非日常な体験や、特別な文化的体験ではなく、日常生活の中に影を潜めるようになった原始的な体験。その体験を少しばかり強調するための道具を制作し、現代社会において鈍化している身体感覚を呼び覚ます。それが自らに課した使命でした。
私たちは珈琲を日常的に口にしています。洗練された店舗、厳選された豆と美味しい珈琲。そういったものは世に溢れています。
しかし、もっと身体に響く珈琲体験はないものか。植物の種子の抽出液であることをもっと生々しく感じられないものか。
その思考の行き着いた先が“すり鉢で珈琲豆を砕き、潰す”という所作であり、その道具の素材や製作方法の検討に進んでいくことになりました。
庵治石ミルの主眼は、その提供体験にあります。
すり棒を通じて焙煎度によって異なる豆の硬さを身体に感じながら、そのすり潰す音、焼かれた植物の種子が粉に変化する様、そして粉砕によってたちまち広がる香ばしい豆の香りも感じ取る。舌のみならず、身体全体で珈琲を味わうことを可能にする道具が、この庵治石ミルです。
造形に関し、すり鉢の有機的な下膨れの形状は、豆をすり潰す際の安定性や豆が飛び散らないようにする機能も果たしています。この曲面の形状が多少変わるだけでも審美性は失われてしまうため、石材を形成する作業は相当な難度となります。
また、すり鉢、すり棒とも様々な粒度に磨き分けられ、粒度変化を表現しています。その相違は外見上の色調のみからでは読み取り難く、“ツルツル”“スベスベ”“サラサラ”“ザラザラ”等、実際に触ると皮膚感覚で違いを感じ取ることができます。
Learn Stories of Makers
醒間|SAMASIMAについて
醒間|SAMASIMAは、感覚を呼び覚ます私的な空間と時間、そしてこれらを創造し、提供する有機的組織。
業種の垣根を超えたメンバーによって現代工芸の企画・制作と、制作した道具によるフィジカルな体験設計を手掛けています。
京都を中心に展示会、イベントを不定期開催し、醒間の体験提供の場としています。
現代社会で鈍化している身体感覚を呼び覚ます、石ミル
醒間が提供する体験。それは、非日常な体験や、特別な文化的体験ではなく、日常生活の中に影を潜めるようになった原始的な体験。その体験を少しばかり強調するための道具を制作し、現代社会において鈍化している身体感覚を呼び覚ます。それが自らに課した使命でした。
私たちは珈琲を日常的に口にしています。洗練された店舗、厳選された豆と美味しい珈琲。そういったものは世に溢れています。
しかし、もっと身体に響く珈琲体験はないものか。植物の種子の抽出液であることをもっと生々しく感じられないものか。
その思考の行き着いた先が“すり鉢で珈琲豆を砕き、潰す”という所作であり、その道具の素材や製作方法の検討に進んでいくことになりました。
庵治石ミルの主眼は、その提供体験にあります。
すり棒を通じて焙煎度によって異なる豆の硬さを身体に感じながら、そのすり潰す音、焼かれた植物の種子が粉に変化する様、そして粉砕によってたちまち広がる香ばしい豆の香りも感じ取る。舌のみならず、身体全体で珈琲を味わうことを可能にする道具が、この庵治石ミルです。
造形に関し、すり鉢の有機的な下膨れの形状は、豆をすり潰す際の安定性や豆が飛び散らないようにする機能も果たしています。この曲面の形状が多少変わるだけでも審美性は失われてしまうため、石材を形成する作業は相当な難度となります。
また、すり鉢、すり棒とも様々な粒度に磨き分けられ、粒度変化を表現しています。その相違は外見上の色調のみからでは読み取り難く、“ツルツル”“スベスベ”“サラサラ”“ザラザラ”等、実際に触ると皮膚感覚で違いを感じ取ることができます。
確信と粘り、そして職人の矜持によって生み出された
醒間立ち上げ時のコアメンバーでプロダクトデザイナーの綾利洋氏(o-lab.inc.)が意匠設計。そして、石材の販売、加工、外構工事等を営む株式会社丸八石材に、庵治石ミルの製作手配を依頼しました。
同社の手配のもと、庵治石の産地の熟練石工に製作いただいております。
いかにして鏡のような光沢度を有するに至るまで磨き上げるか。それが石材加工の通常の世界であり、磨き分けられる際もその境界線は明瞭です。
これに対して、醒間の石ミルのオーダーは、連続的な粒度変化をつける(グラデーション)というもので、その境界線は曖昧。
当然の結果として、当初は職人の美学に則った試作が届くことになりました。迷いのない直線的な磨き分けで、「徐々にラフに仕上げるようなことは難しい」と伝えられました。しかし、できるはずという確信が私たちにはあり、根気よく同じオーダーを繰り返しました。
試作のやり取りを繰り返してある時に届いた石ミル。その外側面には醒間が思い描いていた粒度変化が見事に表現されていました。
職人の美学に反したかもしれない意匠ですが、その職人の矜持によって「庵治石ミル雪解け」を生み出すことができました。
香川の庵治石が石ミルとして仕上がるまで
庵治石は、香川県高松市北東部の庵治町・牟礼町の丁場で採掘される岩石で、地質学的には細粒黒雲母花崗岩。鉱物の結合が緻密であるために、強い硬さを備え、風化もしにくいと言われています。
庵治石は、丁場で採石された後、小割りして石材加工場に運ばれます。そして、パイプで筒型に抜き取られた後は、旋盤で削り出して形成され、13種類にも及ぶ砥石により仕上げられます。
「つくらない」ことが最良の選択肢であり得るということは、常に頭の片隅に
様々な方と協働し、新しいものをつくることは、心躍り、この上なく愉しいことです。そして、人の最低限の生活に必須とは言えないものをあえて新たにつくる以上、作り手側が愉しめるものでなければならないとも考えています。
醒間は企画・設計を行うもので、物理的な意味での製作については依頼する立場になるという前提ではありますが、ものを手仕事でつくることは、それ自体が人の本能的な喜びに繋がっており、人を豊かにするものであると考えています。
様々な思いを廻らせ、作品の企画の着想というのは、常にあります。
しかし、いつ、いかなるタイミングであっても「つくらない」ことが最良の選択肢であり得るということは、頭の片隅に置いています。「もの」が溢れている今日において、企画の着想を「ものづくり」という形で結実させるためには、いくつもの超えるべきハードルがあると思います。
手仕事だからこそ製作可能な自由で有機的な造形はあります。もっとも、大企業でなくとも「手仕事的作品」をより簡易・迅速・低廉に自動製作する時代が、そう遠くないタイミングでやってくるかもしれません。
しかし、工業生産によって手仕事と同じものを作り出せるとしても、手仕事によるものづくりの意義は失われないと思います。それは、繰り返しになりますが、身体的な創作は、それ自体として人に本能的な喜びをもたらすものであり、そのような仕事が尊い職業として存続し得る社会こそが豊かな社会であると言えるからです。
実際に、手に取り、触覚を通じた表現を感じ取って欲しい
工業製品においても、工芸品においても高いデザイン性を兼ね備えたものを目にする機会は多くなりました。「映え」を意識する社会風潮に代表されるように、あらゆる物や空間が、画像データとして流通し、ものごとの評価も視覚から得られる情報にその多くを依拠するようになりました。
しかし、工芸的手法による道具は、ファインアートのように専ら鑑賞することに目的があるのではありません。実際に、手に取り、その触感を味わうこと。工芸品では、購入する前でも触れることが多くの場合許されているので、その実物の触覚を通じた表現を感じ取って欲しいと思います。
石ミルに託した願い
私たちは、美味しい珈琲をリラックスして飲んで頂く体験を提供しているわけではありません。
珈琲豆を砕き、すり潰す過程も含めた珈琲の時間が、身体的に感覚的に丁度良い刺激として心地よいものとなる。それが醒間の提供したい体験です。例えば、それはストレッチのようなフィジカルな刺激に伴う心地よさに類するものです。
そして、いつしか、珈琲をのむ為に豆をすり潰すのではなく、豆をすり潰したいが為に珈琲を飲むという逆転現象を生じさせることが、この石ミルに託した私たちの願いです。
おまけ:作り手の幸せ(西村氏)
植物が好きです。
家庭内では誰からも共感を得ておりませんが、屋外で越冬できる植物を中心に鉢物50鉢程度を育てており、数は増える一方です。
水をやり、枝葉を整理し、新しい鉢に植え替えるなどして、植物と戯れる時間が幸せです。











