木の葉皿
どんな料理も気にせず盛れる使い勝手のいい器
真っ直ぐな杉の木目を木の葉の模様になるように寄木して、一枚ずつ木工ろくろで削り出し、表面を「うづくり」という木目を浮き立たせる仕上げをしています。
やわらかな木肌に漆をたっぷり染み込ませているので、水や油なども染みることがなく、熱にも耐える実用的なお皿です。天ぷらやパスタなどいろいろな料理をのせてお楽しみください。
漆の深い色合いが料理を引き立てるので、見た目もおいしそうに見えてご馳走感が増すのもポイントです。
日常の生活道具として気持ちよく使ってもらえたらと思います。
3センチの角材を寄木する際の接着剤には漆とミルクカゼインとにかわを混ぜたものを使い、細部にまで自然素材にこだわりました。
■ お取り扱いについて
漆塗りをしていますので、汁物、油物もOKです。
洗うときはスポンジなど柔らかいものを使い、自然乾燥してください。
木は収縮しますので、長く水につけること、
食洗機、電子レンジでの高温は負担が大きいのでお控え下さい。
また漆は、紫外線に弱いので、長く日に当たらないように注意します。
漆の塗り直し、修繕も行ないます。
日本国内発送のみ
ショッププロフィール
杉の木クラフト
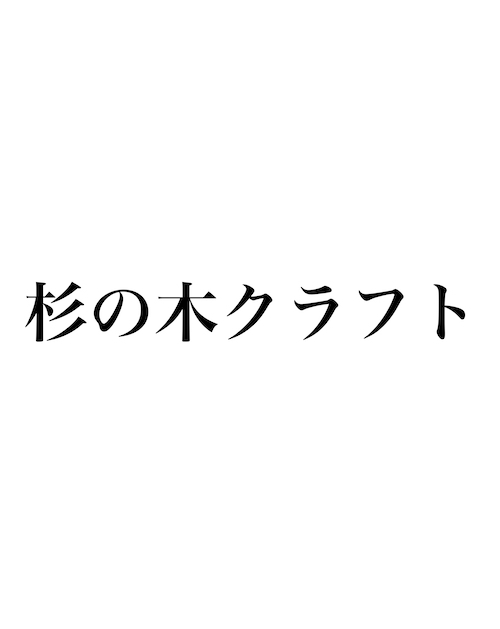
6品
送料(1品ごと): 日本: ¥770このショップでは¥10,000以上のお買い物の際に国内配送料が無料になります。
4~7営業日で出荷
¥5,280(税込)
ポイント還元
52 SeC
色
その他
木の葉皿21cm
¥5,280(税込)
ポイント還元
52 SeC
色
その他
木の葉皿27cm
¥7,150(税込)
ポイント還元
71 SeC
色
その他
木の葉皿30cm
¥8,800(税込)
ポイント還元
88 SeC
カートへ
Transparency Points
透明性項目
品物のハイライト
この品物の注目して欲しいポイント
文化伝統
自然素材・オーガニック
森を守る
匠の技
手作り
作り手
品物の生産に関わった作り手の顔とコメント
溝口伸弥
人も素材も、個性を生かす。
代表
生産地
品物が作られた場所
日本、福岡県糸島市
原材料
品物の素材や原料
自然素材の割合
98%
SDGsへの貢献
この品物がどのSGDsに貢献しているか
影響・効果
社会にどんな影響・効果があるのか
大量消費でなく、少量を大切に長く使うこと
レア度
品物の希少性
この星で唯一
杉の木クラフト
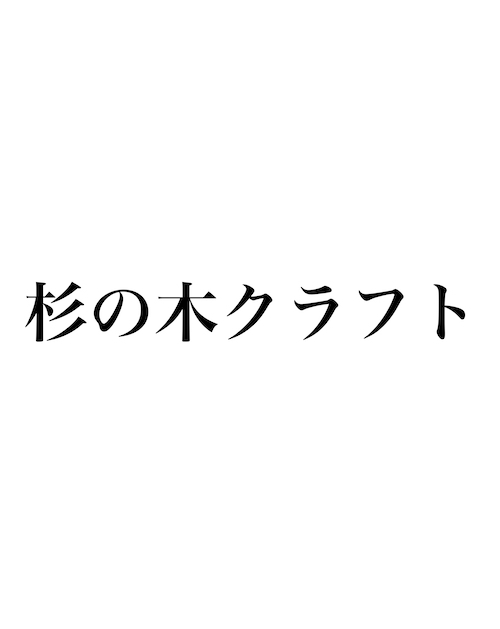
品物一覧を見る
特定商取引法に基づく表記
Story
品物のストーリー
植林された九州の杉を使って、天然の漆で仕上げた「木の葉皿」です。
角材を貼り合わせ、葉脈のように寄木したものから削り出して作ります。
1997年に工芸家の時松辰夫氏によりデザインされました。
杉の木クラフトでは、接着剤も塗料もすべてを自然素材とし、「木の葉皿」を作り続けています。
年輪を浮き立たせる浮造り(うずくり)という技法で、
杉の木の独特な木目と色合い、手触りに仕上げています。
Learn Stories of Makers
杉の木クラフトについて
木工の道を選んだのは「好きなことを仕事にする」と決めたからでした。
自分にとって夢中になってしまうことが、手でモノを作ることでした。
素材は慣れ親しんだ木を選び、さまざまな木があるなかで、
どの木を使うかを考えたとき、「日本の杉の木」がすぐに浮かびました。
日本の森の多くは戦後に植えられた人工林です。
かつて木材は建築や生活道具として使われていましたが、今では新建材やプラスチック製品が広まったことで、あまり使われていません。
世界的には森林破壊が進んでいることが問題になっていますが、日本では植えて成長した木を使っていないことが問題になっています。
「使わないともったいない木」それが杉の木です。
森林を守る林業の仕事は、農業、漁業と同じく人間だけでない生き物すべての基本的な営みです。杉の木を使うことで応援ができます。
林業会社と木工家の時松辰夫氏が生み出した「木の葉皿」は台風で倒れて放置された杉の木を使いました。普通なら捨てられてしまうような木が、美しい工芸品に変わるクラフトの力に感動しました。その事業を引き継ぎ「なんでもないものを魅力的に変える」をテーマに「杉の木クラフト」を立ち上げて20年。今では「うるしの弁当箱」「枝クラフト」など人気商品をもつ福岡県糸島のブランドになりました。
杉の木の特性を生かしきる
「なんでもないものを魅力的に変える」ためには「素材を生かしきること」が必要です。
素材が持つ特性をシンプルな形で、ちょうど良いバランスで表現します。
杉の木の特性は、軽い・真っ直ぐな木目・調湿性・保温性・手触りの良さ・いい香りです。
素材の特性をとことん生かすモノは何かを考え、軽さ・通気性といった杉の木の特性を最大限に引き出すことができるのが、弁当箱でした。伝統的に古くから作られていることにも納得できます。自信を持って「お弁当は杉の木」と勧めることができる理由です。
「天然のもの」へのこだわり
木材の他に使う材料に接着剤と塗料があります。天然素材しかなかった時代と違って今ではボンド、ウレタン塗装などの合成樹脂が主流となっていて、当初は同じように使っていたのですが、せっかくの天然素材に、プラスチックのようなものを挟み込んだり、コーティングしたりすることに抵抗を感じていました。
食品の添加物のように、作る側の都合で使われるものと同じように思いました。食べる人に安全なもの、作る人、使う人に安全なモノであれば、環境にも優しい。伝統的なやり方に着目し、工夫を重ねて、すべてを天然のものでできるようにしました。手間がかかり、難しいのですが、気持ちよく仕事ができるようになりました。
うるしの弁当箱の製造工程
1. 山から切り出した原木を木材市場で購入、製材所で板に加工、工房に桟積みし半年から一年乾燥させます。
2. 木目の詰まり具合や色などチェックし、耐久性の高い赤身のみから部材を用意します。
3. 曲げ加工をする箱の部材は一晩水につけて、熱湯の中で曲げます。
4. 漆と小麦粉を混ぜた接着剤を作り、底板をはめこんで組み立てます。
5. 仕上げ作業ののち、拭き漆を施し完成です。約20日間の工程です。
パッケージは紙類のみで、緩衝材は廃材のカンナ屑(薄く削られた木の屑)を使っています。
使う人の日常に変化をもたらす
「毎朝の日課であるお弁当作りが楽しみになりました。」という購入された方からの声をたくさんいただいています。料理は趣味で楽しんでいる人と、労働と思って楽しめない人がいるので、楽しんでいる人はますます楽しくしてくれる道具になりますし、つらい労働という思いも、楽しみへと少しでも変化をもたらしてくれると思っています。
また「いつもよりご飯が美味しくなる」という感想をいただくことも多いですが、
これは木の水分調整の機能だけでなく、見た目、匂い、手触りといった五感で感じるものがあるからではないでしょうか。
おそらく使ったことのない方には初めての体験になるので、なんらかの感動が生まれるのだと思います。
漆塗りのお弁当箱は使い続けると良い感じに古びていきますが、塗り直しすることでまた長く使い続けることができます。割れたり、欠けたりしてもたいていのものは修理できるのは漆の良いところです。愛着を持ってモノを使い続ける良さがあります。
「愛着」を持てるモノを作る
ものづくりの仕事をしていて、いつも気になるのは大量消費社会です。
モノがすぐにゴミになっていくことです。
「エコバックを何個も持つより、ビニール袋を何度も使う方が環境に優しい」という専門家の意見を聞いたことがあります。
愛着のあるエコバックを一つ使い続けることや、ただのビニール袋でもやぶれるまで使うこと。この「愛着」と「もったいない」の気持ちが大切だと思います。
食べたいだけ食べて健康を損なうのと同じように、地球の資源を使いたいだけ使えば、地球の健康がおかしくなるように思います。
無くなるだけの石油資源などよりも、持続できる森林資源を使って、愛着を持てるモノを作っていきます。



